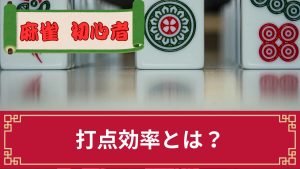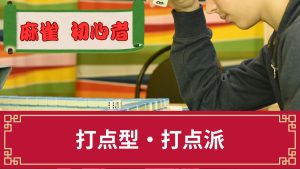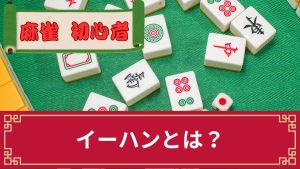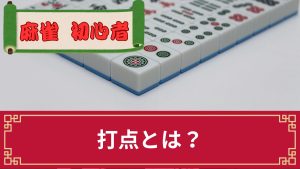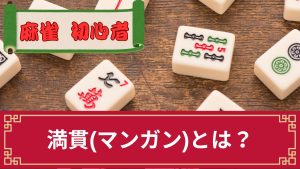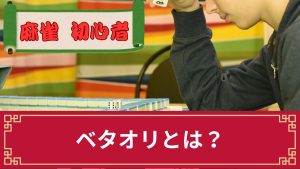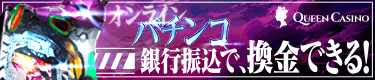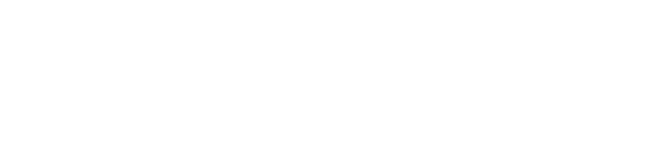麻雀は、ルールを把握できていないとなかなかチャレンジしにくいイメージがありますが、ご家庭などでドンジャラをしたことがある方は多いのではないでしょうか。
麻雀とドンジャラのゲーム性はよく似ているので、ドンジャラをしたことがある方であれば、あまり抵抗感なく麻雀をプレイできるのではないかと思います。
ルールがまったく同じというわけではないので、実際にプレイするにあたっては麻雀とドンジャラの違いを、きちんと把握しておかなければなりません。
本記事では、麻雀とドンジャラの違いを解説しています。
細かいルールにいろいろと異なる点があるので、これから麻雀をプレイしてみたいと考えている方は、参考にしてみてください。
麻雀とドンジャラそれぞれの特徴

麻雀とドンジャラ、まずはそれぞれの違いを見ていきましょう。
麻雀の特徴
麻雀は、4人がそれぞれの手牌を使って役を完成させ和了を目指すゲームです。
牌を引いたり捨てたりしながら手を進め、最終的に役を揃えた得点で勝敗を競います。
また、麻雀は相手の動きを読む心理戦や、状況に応じた判断力が問われる場面が多く、熟練者ほど深い楽しみ方ができます。
一局ごとに展開が変わるため、飽きが来ない点も魅力です。
ドンジャラの特徴
ドンジャラは、麻雀を簡略化した誰でも気軽に楽しめるファミリー向けのゲームです。
ドンジャラでは、キャラクターや絵柄を揃えてアガリを目指します。
麻雀のように複雑な役や計算がなく、初心者や子どもでも理解しやすいルールが特徴です。使用する牌にはアニメやゲームのキャラクターが描かれていることが多く、親しみやすさがあります。
また、ドンジャラのゲーム展開は比較的シンプルで、運の要素が強いです。
そのため、誰もが平等に勝つチャンスがあります。
短い時間で遊べる点も、忙しい日常にぴったりです。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/
麻雀とドンジャラの違い

麻雀とドンジャラは、「牌を使ってプレイする」という部分こそ同じですが、プレイしていくうえで重要な要素に多くの違いがあります。
ここでは、麻雀とドンジャラの違いを紹介します。
牌の枚数の違い
麻雀の牌は大きく
- 「萬子」
- 「筒子」
- 「索子」
- 「字牌」
の4つに分けられ
- 「萬子」
- 「筒子」
- 「索子」
には1~9の9種類が、字牌には東南西北白発中の7種類があります。
これらの牌がいずれも4枚ずつあるので、牌の枚数は合計「9×4×3+7×4=134枚」です。
一方、ドンジャラの牌の枚数は合計81枚ですが、麻雀と違ってすべての牌が4枚ずつと決まっているわけではありません。
多めに入っている牌もあれば少ない牌もあるので、それによって役が成立したときの強さが変わるようになっています。
役の種類の違い
麻雀には
- 「ピンフ」
- 「トイトイ」
- 「国士無双」
などの役が、合計42種類あります(紅孔雀や百万石などのローカル役を除く)。
一方、ドンジャラは商品によって牌の種類が異なるので、役の種類も異なります。
そのため、一概に「何種類」ということはできませんが、10~20種類程度のものが多く、麻雀よりは役を覚えるのが簡単です。
鳴きの種類の違い
麻雀には、「ポン」「チー」「カン」という3種類の鳴きがありますが、ドンジャラの鳴きは「ポン」のみです。
「チー」は、同じ系統の牌で「1-2-3」や「5-6-7」といった並びを作る鳴きですが、牌に「数」という概念が存在しないドンジャラにはチーはありません。
また、ドンジャラには最大3枚までしか入っていない牌もあるので、4枚目を鳴く「カン」が存在しないのも自然なことです。
なお、ドンジャラの種類によっては「ポン」すらもなく、完全に自力で牌をそろえて役を作り上げる必要があるものもあります。
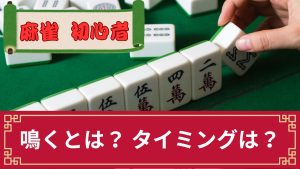
点数計算の違い
麻雀での点数計算は、翻数と符数の2つの要素を用いて行う必要があり、これが初心者の方にとってひとつの壁になることも多いです。
麻雀をある程度プレイしたことがある方でも、カンが入ると途端に点数計算が怪しくなる方も、いるのではないでしょうか。
一方、ドンジャラでは上がり役自体に点数が割り振られているので、難しい点数計算は必要ありません。
ドンジャラをプレイした経験のある人が、麻雀をプレイする場合にもっとも注意しなければならないのは、点数計算かもしれません。

細かいルールの違い
ここまで挙げてきた違いは、麻雀とドンジャラの根本的な部分に関わる違いですが、プレイ中のちょっとした部分においても両者には違いが存在します。
細かいルールにおける違いを、ご紹介します。
プレイ人数
麻雀は、3人でプレイする「サンマ」を除き、基本的に4人でプレイします。
一方、ドンジャラは2~4人でプレイ可能ですし、少人数で遊ぶ場合は専用のミニゲームのような遊び方も用意されており、人数に合わせたさまざまな楽しみ方が可能です。
少人数からでも楽しめるのは、ドンジャラの魅力のひとつといえるでしょう。
回り順
麻雀では、「牌をツモる→手牌から1枚選んで捨てる」という行為を、反時計回り順に行っていきます。
ドンジャラでも基本的な流れは同じですが、反時計回りではなく時計回りの順番で行います。
ある程度プレイを重ねれば慣れてくるとは思いますが、ドンジャラ経由で麻雀をプレイし始めた場合は、順番には要注意です。
王牌の有無
麻雀では、「山」と呼ばれるところから1枚ずつ牌をツモってきますが、山の中には「王牌(ワンパイ)」と呼ばれ、ツモるところができない場所があります。
王牌以外の牌を、すべてツモってきても誰もアガれなかった場合は、流局です。
一方、ドンジャラには王牌の概念がないので、山がすべてなくなるまでプレイを続けます。
フリテンの有無
麻雀では、自分のテンパイ形に含まれる待ちを1種類でも河に捨てていると、「フリテン」と呼ばれる状態になり、他家が捨てた牌に対して「ロン」ができません。
そのため、フリテンの状態では、自分でツモってきてアガる必要があります。
一方、ドンジャラにはフリテンが存在しないので、自分が捨てている牌でも他家からの「ロン」が可能です。
リーチの必要性
麻雀における「リーチ」は役のひとつであり、面前でテンパイした際にリーチをかけるかどうかは、各プレイヤーの判断に委ねられます。
一方、ドンジャラにおけるリーチは、テンパイの状態からアガるために必要不可欠な行為であり、リーチをしていなければ役が揃ったとしてもアガることができません。
カードゲームの「UNO」で、手札が残り1枚になったときに「UNO!」と言わなければ上がれないのと同じと考えると、分かりやすいでしょう。

麻雀が向いている人の特徴
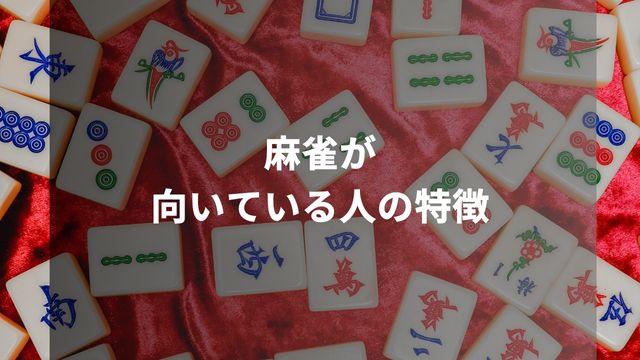
ここでは、ドンジャラよりも麻雀のほうが向いている人の特徴を、ご紹介します。
戦略的なプレイを楽しみたい
麻雀は、ドンジャラと比べると牌・役・鳴きの種類が、いずれも多いです。
ドラや翻・符といった概念があり、点数計算もドンジャラより複雑なので、初心者にとってはハードルが高いかもしれません。
しかし、それは裏を返せばドンジャラよりもできることや考えることが多いことの裏返しであり、戦略や思考に幅があることを意味します。
麻雀には、いわゆるセオリーと言われるような打ち方や考え方はありますが、点数状況や場況によっては、セオリーから外れた打ち方のほうが理にかなっていることもあります。
刻一刻と変化する状況に瞬時に対応しながらプレイする必要があるので、より戦略的なプレイを楽しみたい方には、麻雀の方が向いているといえるでしょう。
友達や家族以外とも楽しみたい
ドンジャラは自宅で家族や兄弟と楽しんだり、友達の家で友人同士で楽しんだりするのが一般的です。
麻雀は、そのような楽しみ方もできますし、雀荘やオンラインゲームなどで友達や家族以外と楽しむことも可能です。
友達や家族と一緒にプレイするのももちろん楽しいですが、雀荘ならこれまで接点のない方と打つことで新しい発見があったり、自分の引き出しが増えたりする楽しみもあります。
オンラインゲームなら、世代や国籍を超えた人と麻雀を楽しむことが可能ですし、定期的に大会を開いていることも多いので、自分の実力を試すのにもってこいです。
打つ場所やシチュエーションを変えてマンネリを避けやすいのは、麻雀を取り巻く環境の大きな魅力のひとつかもしれません。
ちょっとした時間に楽しみたい
ドンジャラをプレイするためには、マットや牌などを準備しなければなりませんし、一緒にプレイしてくれる家族や友人も必要です。
そのため、「プレイしたい」と思ったときに、必ずしもすぐにプレイできるとは限りません。
自分はもっとプレイしたいと思っても、友達が「飽きた」といえば、その時点で終わりになってしまうでしょう。
一方麻雀であれば、雀荘に足を運べばすぐにプレイできますし、アプリならログインしてエントリーするだけですぐにマッチングが行われて対局が始まります。
ドンジャラにもアプリがあることはありますが、麻雀と比べるとプレイ人数が少ないのでログインしてもすぐに遊べるとは限らず、待たされることも考えられます。
作業の合間や寝る前のちょっとした時間でも、プレイしたいと思ったときにすぐにプレイしたい方には、麻雀が向いているといえるでしょう。

ドンジャラが向いている人の特徴

ここでは、麻雀よりもドンジャラが向いている人の特徴をご紹介します。
難しく考えずに楽しみたい
ドンジャラは麻雀よりもルールが簡単で、牌の種類や役の種類も少ないですし、難しい点数計算も必要ありません。
ドンジャラも麻雀も、「不要な牌を捨てながら必要な牌を集めて、他の人よりも先にアガる」というゲームの根幹的な部分は同じです。
ただ、麻雀はそこに加えて打点の考慮や場況の判断、他家に対するケアなど、考えなければならないことが増えます。
楽しいと思うかどうかは人それぞれですが、考えなければならないことが多いとゲームを楽しめないという方もいるでしょう。
そのような方には、麻雀よりもやることや考えることがシンプルで、ルールさえ覚えてしまえば誰でも楽しめるドンジャラのほうが向いています。
子供と一緒に楽しみたい
ドンジャラは、麻雀よりも子供と一緒に楽しむのに向いているゲームです。
ドンジャラは、いろいろなメーカーからさまざまな種類のものが発売されていますが、ドラえもんやワンピースなど、子どもに人気のキャラクターが図柄として多く採用されています。
そのため、子供も自然と興味を持ってくれるでしょう。
「ルールがシンプルで分かりやすい」という点も、子供と一緒にプレイするうえでは大きなメリットです。
子供との接点を増やしたいと考えている親の方にとって、大人でも子供でも平等に楽しめるドンジャラは、非常に便利なゲームです。
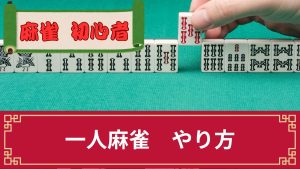
麻雀とドンジャラはどっちがおすすめ?

麻雀とドンジャラのどちらを選ぶかは、遊ぶ目的や参加する人の年齢などによって決めるとよいでしょう。
以下では、状況別に麻雀とドンジャラのどちらで遊ぶのが適切か解説します。
家族や子どもと遊ぶ場合はドンジャラ
家族や子どもと一緒に楽しむ場合は、ドンジャラがぴったりです。
親しみやすいルールと明るいデザインが、誰でも簡単に楽しめるからです。
ドンジャラは、絵柄を揃えるだけで遊べるシンプルなルールのため、子どもでも理解しやすく、初めて遊ぶ場合でも戸惑うことがありません。
また、キャラクターやカラフルなデザインは視覚的に楽しく、ゲームへの興味を引き出してくれます。
複雑な計算や専門的な知識が不要なため、家族全員が気軽に参加できる点も魅力です。
また、ゲームの進行が早く、短い時間でも遊びやすいメリットがあります。
長時間の集中が難しい小さな子どもでも飽きずに楽しめます。
戦略性のあるゲームを楽しみたい場合は麻雀
じっくり考えながら戦略を楽しみたい場合には、麻雀を選びましょう。
多彩な役やルールが組み合わさり、深い駆け引きが楽しめます。
麻雀では、手牌の作り方が勝敗を左右するゲームです。
相手の捨て牌から意図を読み取ったり、役を効率よく作るために必要な牌を引き寄せたりする工夫が求められます。
また、リーチやドラの活用など、戦局に応じた判断が重要です。
こうした要素が加わることで単なる運だけではなく、経験やスキルがゲームの結果に影響を与えます。
さらに、対戦相手との心理戦も麻雀の醍醐味です。
相手の意図を推測し、自分の手を隠しつつ有利に進める工夫が楽しさを倍増させます。
ゲームが進むにつれて状況が変化し柔軟な対応が求められるため、毎回違った体験が味わえます。
初心者の場合はドンジャラ
麻雀とドンジャラのどちらを始めるか迷っている場合は、まずはドンジャラから始めるのがおすすめです。
ドンジャラのルールが麻雀に比べてシンプルで、短時間で気軽に楽しめるからです。
麻雀は様々な役があり点数計算も複雑で、覚えることがたくさんあります。
そのため初心者にとっては、ルールを覚えるだけでもハードルが高く感じてしまうかもしれません。
一方、ドンジャラは同じ種類の牌を3つ集めるというシンプルなルールで、点数計算も簡単です。
そのため、短時間でルールをマスターでき、すぐにゲームを楽しめるでしょう。
また、ドンジャラは運の要素も大きく、初心者でもベテランに勝つチャンスがあります。
ドンジャラから始めることで、ゲームの楽しさを知り、徐々に麻雀に挑戦する意欲が湧くかもしれません。
まずは簡単なゲームから始めて、徐々に難易度を上げていく方が、長く楽しく続けられるでしょう。

麻雀とドンジャラの違いをきちんと把握しよう!
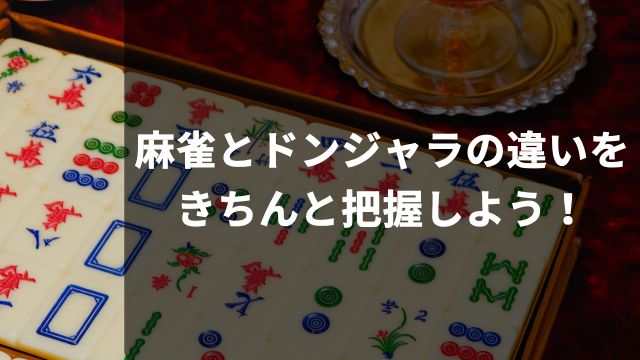
麻雀とドンジャラは、ゲーム性としては非常に良く似ていますが、細かいルールなどに目を向けると多くの違いがあります。
そのため、よく「ドンジャラをやったことがあれば、すぐに麻雀もできるようになるよ」と言う人がいますが、あれはある意味正解でもあり間違いでもあります。
ドンジャラを経由して麻雀をプレイする場合、何が同じで何が違うかをきちんと把握しなければ、麻雀の面白さに触れる前に麻雀を嫌いになってしまうかもしれません。
麻雀とドンジャラの違いが分かれば、自分にとってより楽しめるのがどちらかも自ずと分かると思いますので、まずは両者の相違点をきちんと把握しましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/